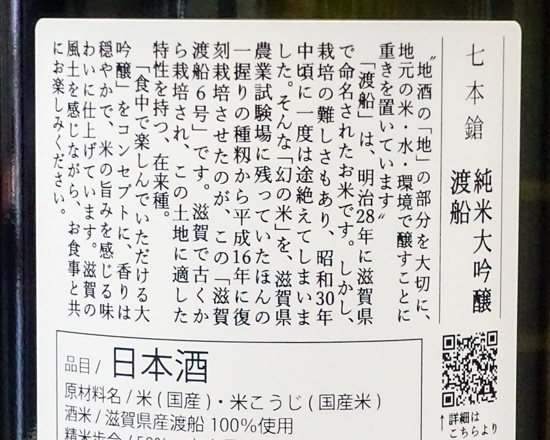■ご注文方法
オンラインでのご注文は24時間受付けております。
ご注文されますと、すぐに自動返信メールがお客様あてに送信されます。その後24時間以内に改めて、お支払い金額、発送日、配達予定日などをメールにて連絡いたします。
メール・お電話・FAXでのご注文も承っております。御中元、御歳暮などギフト・贈答用も対応させていただきます。
※お電話でのご注文、お問い合わせは、営業時間内にお願いします。
営業時間 9:00〜19:00
TEL:0749-62-3170
FAX:0749-62-8192
|
 
■お支払方法
お支払い方法は、代金引換・銀行振込(先払い)・クレジットカードとなっております。
|

■実店舗と連絡先
近江の地酒 はしもとや
〒526-0015 滋賀県長浜市神照町847
TEL:0749-62-3170
FAX:0749-62-8192
e-mail:info@oumi-jizake.com
実店舗営業時間:AM9:00〜PM7:00
定休日:毎週火曜日
滋賀の日本酒と全国の焼酎・梅酒・リキュール お取り寄せ・取扱販売店。御中元、御歳暮などの贈答用、ギフト対応もいたします。 |
|
■配送ついて
配送はヤマト運輸を使用いたします。
在庫のある商品につきましては、ご注文日より 1〜3日でお届けできます。正確な配達日につきましては、お客様からのご注文を確認後、メールにてご連絡いたします。
また、在庫切れの商品については、次回入荷予定日などをご連絡させていただきます。 |
 
■送料
お荷物1個口につき下の表の送料が必要となります。また、クール便での発送には、別途クール料金((330円〜880円・サイズ別に加算)が必要です。
※送料無料について
一箇所の配達で、商品のお買い上げ合計金額が17,000円以上の場合、送料は当店にて負担させていただきます。ただし、北海道と沖縄を除きます。なお、クール便をご利用の場合は、クール料金が必要です。
地
域 |
関東 |
信越 |
南東北 |
北東北 |
北海道 |
送
料 |
970 |
970 |
1,070 |
1,180 |
2,370 |
(円:税込)
地
域 |
中部
北陸 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
送
料 |
880 |
880 |
880 |
970 |
970 |
2,760 |
|

■個人情報の保護について
お客様とのやり取りの中で得た個人情報は、法律によって要求された場合以外、第三者に譲渡または公表する事は決してございません。どうぞ安心してご利用下さい。 |
 |